ロッドの改造(計画)数年ぶりの新ページ登場となった今回の題目はロッド改造。
ロッドをブランクスから作る”ロッドメイキング”ではなく、市販のロッドを数本継ぎのパックロッドに改造するという”ロッドリメイキング(ロッド改造)”だ。 「ブランクスからロッドを作るより市販品を改造すれば安くて簡単だろう」という安直な考えで、ロッド制作未経験の作者がロッド改造に挑戦した。 逆印籠継ぎと継ぎの材質、継ぎの部分をどうするのか、ロッドの長さを測る
ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さ 継ぎ(ソリッド)のサイズ、ロッド切断と補強、継ぎの加工、ダメロッド改造完成? まずはダメロッドで挑戦まずは試作として2ピースロッドの穂先側しかない「使えないロッド=ダメロッド(実は布団叩きに使っている)」で挑戦する。 ダメロッドを4本に切断そして継げるように改造、さらに4本どれもが同じ長さにするのが目的だ。 逆印籠継ぎと継ぎの材質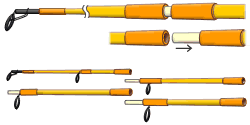 ロッドの継ぎの種類には印籠継ぎ・逆印籠継ぎ・並継ぎ・逆並継ぎがある。 ロッドの継ぎの種類には印籠継ぎ・逆印籠継ぎ・並継ぎ・逆並継ぎがある。今回はグラスやカーボン製ロッドで一般的な逆印籠継ぎを採用した。 逆印籠継ぎのイメージ。継いだときに5mmの隙間が空くようにする。これは制作の誤差を吸収する意味と継ぎの部分が摩耗することを考えたためだ。 継ぎの部分(上図の白い部品)には、釣具屋で販売されているロッド用ブランクの「ソリッド」が入手のしやすさと適度な強度の面でよい(らしい)。 早速店に行くと、いろいろな太さとテーパー(先が細くなる形のこと)のソリッドが同じ長さで数種類売られていた。 価格はその体積(重さ)に比例しており、悩んだ結果ダメロッドとテーパーの角度が似ていると感じたものを購入した。 高さ1200mm、竿先の直径1.2mm、竿尻の直径9mmで540円、当然ロッドを買うより安い。 継ぎの部分をどうするのかまず「ロッドをどの長さで切断するのか、継ぎの部分をどうするのか?」を決めないといけない。 継ぎの部分についてはネットでみつけた以下のことを利用する。
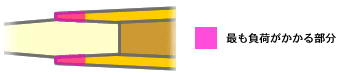 継ぐことだけを考えると図のように負荷がかかり良くないが、口周りを補強すること・接着剤で接合することでカバーできると思う。 逆印籠継ぎと継ぎの材質、継ぎの部分をどうするのか、ロッドの長さを測る
ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さ 継ぎ(ソリッド)のサイズ、ロッド切断と補強、継ぎの加工、ダメロッド改造完成? ロッドの長さを測るロッドの長さはロッドを床に置きメジャーで測るのだが、床に接している部分の長さ(ロッド側面の長さ)がロッドの正確な長さではない。
しかし次の計算結果からロッドの長さはロッド側面の長さと同じと考えていい。 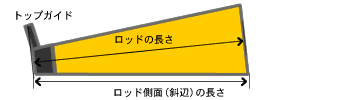 ロッドが床に接している部分の長さは”ロッド側面(斜辺)の長さ”となり、ロッドの長さより長くなる。 ロッドはソリッドと同じように極端に細長い円錐形の先端を切った形であり、ロッドの縦断面は台形となる。 ロッドの長さはロッドの縦断面を台形とみなすことで次の関係式からもとめることができる。 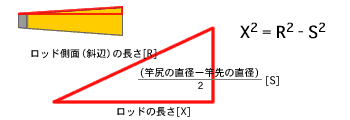 中学で習う三角形の定理を使えばロッドの長さが求められる。 中学で習う三角形の定理を使えばロッドの長さが求められる。ロッド側面の長さ R = 940mm、 竿先の直径 = 1.7mm、 竿尻の直径 = 8.1mmから、 ロッドの長さは X = 939.99 = 940mmとなる。 結論は、 せっかく計算で求めたがロッド側面の長さと同じということだ。 またロッドから突き出た部分「トップガイドの長さ[N]」はノギスを使い下図の方法で測ると トップガイドの長さ(N) = 6.8mmとなった。 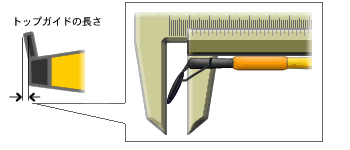 逆印籠継ぎと継ぎの材質、継ぎの部分をどうするのか、ロッドの長さを測る
ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さ 継ぎ(ソリッド)のサイズ、ロッド切断と補強、継ぎの加工、ダメロッド改造完成? ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さロッドの全長と切断する長さの関係は次のようになる。
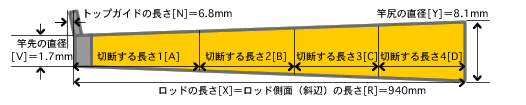 940 = A+B+C+D さらに継ぎのテーパーの長さ(L)と切断する長さとの関係は 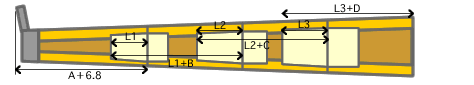 A+6.8=L1+B=L2+C=L3+D 継ぎのテーパーの長さ(L)は下図のようになる 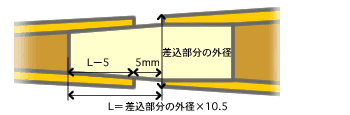 差込んで中に入る分の長さ、外に出ている分の長さ5mmに分けて考える。 そして既に書いたが、継ぎのテーパーの長さは差込部分の外径の10.5倍となる。 ロッドの横断面を図に書いて、ロッドの中心軸をX軸、 竿先を原点0、ロッドを切断する位置をX1・X2・X3、切断位置でのロッド半径をY1・,Y2・Y3、ロッド外側のテーパーを1次関数(直線)としたのが次の図。 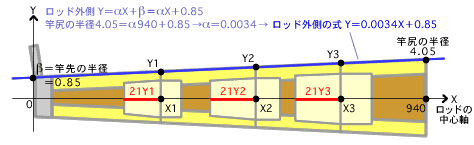 ロッド外側のテーパーの式は図から Y=0.034X+0.85となる。 Yはロッドの半径、テーパーの長さは差込部分の外径の10.5倍だから、 テーパーの長さL=差込部分の外径×10.5=2Y×10.5=21Y 既に出した継ぎのテーパーの長さ(L)と切断する長さとの関係から 6.8+X1 = 21Y1+X2ーX1 = 21Y2+X3ーX2 = 21Y3+940ーX3 の連立方程式ができる。 あとはこれを解けばよいのだが、解き方を間違えると得られる値も誤ったものとなるので、解き方の手順を簡単に説明しておくと、
継ぎ(ソリッド)のサイズ継ぎのテーパーの長さが出たので
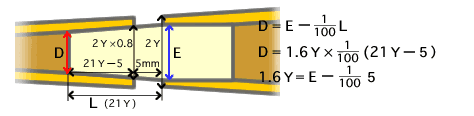 上図の式から継ぎの先端と末端の直径が求まる。 ガイドの位置を考えたロッド切断の長さようやくすべての位置が決まったのだが、「ロッドを切断する長さX2=510mm」をダメロッドに当てはめてみると、下図の位置になる。
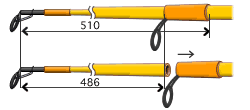 ガイドの後ろで継ぐには強度に不安があったため、切断位置はガイドの手前の486mmにずらすことにした。 ガイドの後ろで継ぐには強度に不安があったため、切断位置はガイドの手前の486mmにずらすことにした。このため、ロッドの長さは1本目と4本目のみ同じで2本目は短く3本目は長くなる。 逆印籠継ぎと継ぎの材質、継ぎの部分をどうするのか、ロッドの長さを測る
ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さ 継ぎ(ソリッド)のサイズ、ロッド切断と補強、継ぎの加工、ダメロッド改造完成? ロッド切断と補強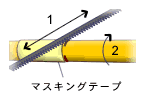 まず計算で求めたロッドの切断位置をマスキングテープでマークする。 まず計算で求めたロッドの切断位置をマスキングテープでマークする。切断には目の細かい鋸を使用する。 鋸を少し引き、次にロッドを少し回す、を繰り返して切断すると失敗が少ない。 切断後、切断面を紙ヤスリで平らにする。 次に補強の「口巻き」の工程を行う。 口巻きはロッド口径を削って広げる時とロッドを継いで使用する際の補強のために行うもので、マスキングテープ、ロッド製作用に販売されている糸「スレッド」、2液性エポキシ系接着剤、PE等の細い糸を使用する。 より見栄えをよくするのであればロッド制作用に販売されている2液性エポキシ系コーティング剤も使うが、2000円ほどすることとコーティングを2液性エポキシ系接着剤で代用できるか試すために今回は使用しない。 用意したPE等の細い糸は輪を作りほどけないように結んで、5cm以上の長さで切っておく。 まずスレッドを巻く「補強する長さ」を決め、マスキングテープを巻く。 巻く最後にスレッドをマスキングテープにはさんで止める。 ロッドを左手に持ち、スレッドを右手で少し張りながら、ロッドをゆっくり回していく。 このときスレッドがゆるまないよう、ライン同士が重ならないように注意する。 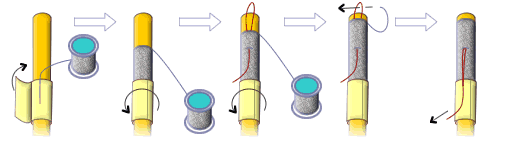 巻いたスレッドの間に隙間ができやすいので、巻きながら空いている指の爪先で隙間をたまに詰めてやるとよい。 ロッド切断面から約1cmほどのところまで巻いたら、先に作った細い糸の輪をロッドに沿わせ、その上からスレッドを巻いていく。 巻終えたところでスレッドを切る。 このとき、左手でロッドと巻いたスレッドを押さえておく。 ロッド切断面側からはみ出した輪の中に、スレッドの先端1cmほどを入れる。 輪の根元を引っ張って輪を引き抜くと、スレッド先端が巻いたスレッドとロッドとの間に隠れる。 マスキングテープからスレッドを外し、1cmほどほどいてから輪を使って同じ方法でスレッド先端を隠す。 最後に指の爪先で巻いたスレッドを詰めて整える。 2液性エポキシ系接着剤をロッドを回しながら接着剤付属のヘラを使って塗っていく。 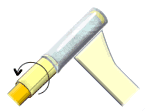 このとき、あまり厚塗りしないように注意する。 このとき、あまり厚塗りしないように注意する。巻いたスレッドの凹凸がなくなるぐらいの厚さに塗るのがよい。 また、ロッド切断面側はロッド内側に接着剤がつかないように注意する。 マスキングテープ側はテープ側に少しはみだすように塗る。 塗り終えたらゆっくりとロッドを水平にして回し、接着剤がたれなくなるまで待つ。 マスキングテープを慎重に剥がすと、コーティングの境がきれいな直線となる。 瓶などでロッドを立てて乾燥させる。 気温によるが、24時間以上で硬化するのでそれまでは何もせずに置いておく。 冬場は電気ストーブの手前に置くと硬化が早いが、たまにストーブにあたる面を変える必要があるのと、ストーブとの距離が近すぎ温度が高すぎると気泡が発生してしまうので注意する。 継ぎの加工先の計算で出した必要な継ぎ(ソリッド)の太さと長さを元に、ノギスと定規で用意したソリッドを測り、適切な部分を鋸で切り出す。 ソリッドの切断面を紙ヤスリで整え、切断面を正円形にする。 ソリッドを左手に持ちゆっくり回しながら、右手でやすりがけを行う。 頻繁にノギスと定規を使って目的のテーパーと形に加工する。 実はこれが正確さと根気が必要とされかなり難しい。 特にテーパーの角度の調整は職人技だ。 電動ドリルやボーリング盤があればその先にソリッドを固定し回転は機械にまかせて、後はヤスリがけの角度を気を付ければ簡単で早そうだが、手で回す場合は難易度が高い。 削りすぎたらアウトなので、この段階では僅かに太いぐらいでよい。 今度はロッド側の加工である。 これにはノギスと数種類の太さの棒ヤスリ(断面が円形のもの)を使う。 ロッドを左手で回しながら右手の棒ヤスリでロッド内径を広げていく。 ノギスで口径をたまにチェックしながら行う。 最も難しいのがこの穴を広げる作業だ。 理想は継ぎのテーパーと同じ角度をもつヤスリで加工するのだがそんなものは特注しない限りは入手できない。 代わりにあらかじめ継ぎのテーパーと同じ角度のソリッドを作っておき、それに紙ヤスリを巻き付けて使う方法があるが、実際にやってみるとなかなかうまくいかないことがわかった。 特にロッドが細い場合は無理である。 ある程度穴が加工できたら、作ったソリッドを差込んでみる。 つかえたところでソリッドを回し、引き抜く。 ソリッドが太いもしくは穴が小さいためにつかえるのだが、つかえた箇所はソリッドに跡がつくはずである。 ソリッドの跡のついた箇所もしくは穴のそれらしい箇所をヤスリがけする。 再びソリッドを差込み、回してから引き抜く。 そして再びヤスリがけを慎重に行う。 ひたすらこれを繰り返す。 ソリッドが目的の長さ差し込めて、ソリッドの表面全体に跡がつくようになるまで加工を行う。 継ぎはある程度きついほうが抜けにくくてよい。 最後にソリッドの根元に2液性エポキシ系接着剤を薄く塗ってロッドに差込んで24時間乾燥させる。 そして口巻き部分をマスキングテープと接着剤を使って再度コーティング・乾燥させる。 以上のロッドの切断と口巻き、穴とソリッドの加工を、すべての箇所に行えば完成だ。 逆印籠継ぎと継ぎの材質、継ぎの部分をどうするのか、ロッドの長さを測る
ロッドを切断する長さと継ぎ(ソリッド)のテーパーの長さ 継ぎ(ソリッド)のサイズ、ロッド切断と補強、継ぎの加工、ダメロッド改造完成? ダメロッド改造完成?このページ作成と同時進行のため10日以上かかったが、ようやくダメロッドの4本継ぎが完成した。 完成したロッドを振ってみると改造前と比べて少し固めとなった。 これは「口巻き部分=硬い部分」が増えたためかもしれない。 ロッドのアクションは改造前と比べて変わった感じはなくミディアムテーパーだった。 失敗点もある。 この改造ロッド、なんどもすばやく振ると、先端の部分がすっぽ抜けてしまう。 ソリッドを削りすぎ継ぎが少しゆるめであることと、振ったときにかかる遠心力は竿先にいくほど大きいために抜けてしまうのだ。 このため竿先の継ぎ部分は他の部分に比べより高い完成度(継ぎの密着度)が必要だ。 「継いだ部分の摩擦の大きさ」は「抜けにくさ」につながる。 ロッドが細いほど継ぎの部分の表面積は減るため、摩擦が減ることにつながるのである。 そして継ぎの差込部分のテーパーを計算どおりに加工することは、ロッドが細くなるほど難しい。 実際作った3箇所の継ぎのソリッド部分は計算値より細くなり、竿先の穴の形状の加工は、棒ヤスリのテーパーと同じようにしかできなかった。 また2液性エポキシ系接着剤でスレッドのコーティングを行ったが、かなり気泡が入ったのと乾燥後もベタつきの残る箇所があった。 白い小さな円が気泡。塗った時は出なくても乾燥中に発生する場合もある。 2液性エポキシ系コーティング剤をためしたことがないので比較はできないが、透明度については問題なく、接着剤の方が粘性が高く固化が早いと思う。 市販ロッドと同じ完成レベルを目指すとなるとコーティング剤でないと難しいが、それでなければ接着剤でももう少し使い方を工夫すれば代用が可能だ。 次回は改造のために1980円で買ってきた2ピースロッドで挑戦するがそれには以下の点をどうするかが課題である。
|