ルアーのデザインと浮き方の関係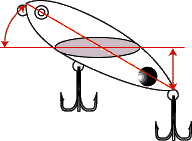 ルアーを作っていざ水に浮かべてみると、考えていた浮き方と違ったり思うように動かなかったりする失敗はよくある。 ルアーを作っていざ水に浮かべてみると、考えていた浮き方と違ったり思うように動かなかったりする失敗はよくある。木材の加工・塗装などでの失敗は目に見えるのでわかるが、ルアーの浮き方・動き方はスイムテストをしてみないとわからないもの。 そこで作る前にあらかじめルアーデザインからルアーの浮き方を予想しようというのがこのコーナーだ。 ルアーデザインとはルアーの製作を始めるとき、普通はまずどのようなルアーを作るのか決めると思う。
”こんな形をしたもの”とか”こんな動きをするもの”といったことを考えながら形・ 大きさ・アイの取付け位置・ウェイトの位置、そして色や模様などを決めていく。 これがルアーデザインだ。 ひらめきや感覚をもとに作ったルアーは、稀に意外な秀作も生まれたりするが、だいたいは思い通りの動きをしてくれないもの。 ルアー作りの経験を積めばなんとなく、その浮き方・泳ぎ方が予想できるようになるが、それははっきり言い表せない程度でとまっている人がほとんどだと思う。 そこで、いくつかの簡単な原理が分かっていればデザインしたルアーの浮き方・泳ぎ方がある程度予想できるかもしれない、そんな期待をしながらこのコーナーではルアーのデザインと浮き方の関係について考えてみた。 簡単な原理と特徴ルアーにはいろいろな種類があるが、今回はサーフェイスプラグ(トップーウォータープラグ)について考えてみることにする。
このタイプのルアーは、浮き方・泳ぎ方が目で見えるのでこのコーナーに最適だ。 サーフェイスプラグでは、その浮き方が泳ぎ方に大きく影響する。 ルアーの浮き方を決定するのはルアーと水の特徴だ。ルアーの特徴のうち浮き方と泳ぎ方に関係すると考えられるのは
その結果が
また、水と水に浮く物の特徴(原理)として
わかりやすいように右図に示した。 これら4つの特徴が影響して浮き方が決まるのではないだろうか? 具体例円柱まずは最もシンプルな円柱で考えてみる。
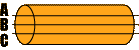 右図のように浮くことは誰でもわかるが、なぜ立った状態や斜めの状態で浮きにくいのだろうか? 右図のように浮くことは誰でもわかるが、なぜ立った状態や斜めの状態で浮きにくいのだろうか?それには先ほどの4番目の特徴が関係している。 横になった状態が一番面積が大きいのだ 。 そして沈み具合は1番目と3番目の特徴により決まる。 A、B、Cは水面の位置で、Aの状態が円柱が重い場合、Cの状態が軽い場合。 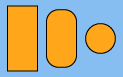 横になって浮いている場合、斜めになって浮いている場合、縦になって浮いている場合の”4”の部分(真下から浮いているものを見たとき、ちょうど水面の部分での断面図)を現したのが右図だ。 横になって浮いている場合、斜めになって浮いている場合、縦になって浮いている場合の”4”の部分(真下から浮いているものを見たとき、ちょうど水面の部分での断面図)を現したのが右図だ。横になった状態が一番断面積が大きいのは明らかで、安定しやすい体勢なのだ。 これは水の上だけでなく地面の上に物を置く時でも同じ。 水面に接する部分が多い方が安定しやすい。 角材角材の場合、木の重さ(比重)によって浮き方が変わる。
なぜなら円柱はいくら転がしても同じだが、角材は角があるため、安定になる場合が変わってくるのだ。 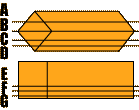 どのように変わるのかというと、比較的角材が重い場合はA、B、C(Aが角材が一番重い場合)の状態で浮き、それより軽ければFの状態で浮く。 どのように変わるのかというと、比較的角材が重い場合はA、B、C(Aが角材が一番重い場合)の状態で浮き、それより軽ければFの状態で浮く。Dの状態で浮かないのは、特徴4の”水面の位置での断面積”が関係していてDよりFの方が水面での断面積が大きいためだ 。 E〜Gの状態で浮くかどうかは、角を下にして浮く(A〜Dの)状態と平らな面を下にして浮く(E〜Gの)状態を比べてみて、特徴4の”水面の位置での断面積”がどうなるのかによる。 特徴1と3から木は重いほど沈み、水に使っている部分の重さとその部分の体積に相当する水の重さが同じになるまで木は沈む。 角材の重さから、角を下にして浮く場合(A〜D)のどれで浮くのか、平らな面を下にして浮く場合(F〜G)のどれで浮くのかを考えて、その2つを比べてむ。どちらの場合が特徴4の”水面の位置での断面積”が大きいのかを比べて、大きい方の体制で浮くことになる。 角材の形と重さによっては、この2つの浮き方で、特徴1の”水に浸かっている部分の体積”と特徴4の”断面積”のどちらもが同じことがある。 この場合どうなるのか? この場合はどちらの浮き方もあると思う。 けれども実際のルアーではアイやフック、ウェイトがあるため特徴2の”物のより重い部分が下を向きやすい”も関係してくるので、このようなケースは考えなくてよいだろう。 ペンシル右の図はペンシルタイプだ。 前が太く後ろがだんだん細くなっている。 さてどんな浮き方をするのか? 重さが軽い、中位 、重いの3つの場合を考えてみる。 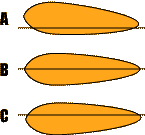 まず軽い場合。 まず軽い場合。軽いので、特徴1と特徴3からあまり水に沈まない。 そして4番目の特徴を考えると、おそらく右図のAのように、少し後ろのほうが下がった体勢で浮くのではないだろうか? ただしその角度は木の比重により変わってくる。 次に中位の重さの場合、1番目と3番目の特徴から、軽い場合より少し水に沈むことが予想できる。 しかし4の性質についてはよくわからない。 そこで2番目の特徴について考えると、頭と尾では頭の方が重いため頭の方がより沈み、その結果右図のBのようにほぼ水平に近い形で浮くと考えられる。 そして重い場合。 特徴1と特徴3の性質から、さらに水に沈む。 そして2の性質から尾より頭が重いため、頭は沈みぎみになり、 その結果右図のCのように頭が尾より少し下がった姿勢で浮き、水上から見た時、ほとんどルアーは背中のみであまり見えないだろう。 もちろん木の比重によってこの浮く角度も変わる。 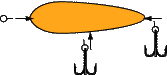 ここまでは、ただの木について考えたが、今度は実際のルアー、アイとフックがついたノーウェイトのルアーについて考えてみる。 ここまでは、ただの木について考えたが、今度は実際のルアー、アイとフックがついたノーウェイトのルアーについて考えてみる。先ほどのペンシルの形をした木材に、右図のようにアイとフックを取付ける。この場合、B(木が中位 の重さの場合)について考えてみよう。 アイとフックを取付けたため、ただの木の場合により全体の重さはより重くなっている。 そのため特徴1と特徴3から、より水に沈む。 そしてフックの部分がより重いため、特徴2から後ろの方がより沈み、その結果としてAのような頭が少し上を向いた体勢でさらに水に沈んで浮くと予想できる。 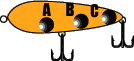 今度はさらにルアーにオモリを入れた場合を考えてみよう。 今度はさらにルアーにオモリを入れた場合を考えてみよう。オモリ1つを右図のA、B、Cの3箇所にいれた3つの場合について考える。 そしてオモリはルアーの浮き方が変わるぐらいの重さとし、木の重さは中位とする。 Aの部分にオモリがある場合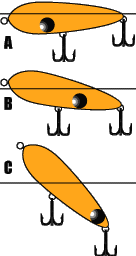 先程はフックのあたりがより重かったのだが、今回はセンターフックより少し手前の方が重くなる。 先程はフックのあたりがより重かったのだが、今回はセンターフックより少し手前の方が重くなる。そのため特徴2の”より重い部分が下を向きやすい”ということから、センターフックのあたりがより下を向いた姿勢となり、結果として右図のAのよう浮くのではないだろうか。 そして特徴1と特徴3からノーウェイト(オモリの入っていない状態)のときより水に沈むと考えられる。 Bの部分にオモリがある場合ルアーの重い部分はBだから、2の特徴から、Bの部分がより下を向く体勢となり、特徴1と特徴3から水により沈んで浮くことになる。
その結果 、後ろのほうが前の方より沈み、右図のBのような体勢で浮くと考えられる。 Cの部分にオモリがある場合。ここまで説明してきた考え方がなんとなくわかってくれば、簡単だ。
特徴2の、ルアーでより重い部分はどこか? ルアー全体の重さはどのぐらいか? 重い部分は後部で、ルアー全体はちょっと重く、ボディ全体の半分より少し多めが水に沈むので、 頭はかなり上を向いて浮くことになる。 つまり右図のCのように浮くと予想できる。 もちろん木の比重、ボディの太さによってはより垂直に浮く場合がでてくる。 ここまで簡単にルアーの浮き方を予想してきたが、これらはあくまで限られた例にすぎない。 木の比重、フックの位置と重さ、オモリの位置と重さ、ルアーの形、ルアーの大きさと太さ、これらの組み合わせによって、浮き方が変わってくる。 だが浮き方とは簡単に言えばどれぐらい沈むのか、どれぐらいの角度の体勢になるか、ということだ。 重い程沈み、ルアーの重い部分と軽い部分の差が大きい程、重い部分の位置によりルアーの浮く角度がはっきりと変わる、ということがわかっていれば浮き方の予想はある程度できるようになると思う。
|